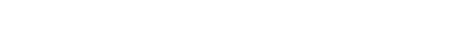e-LOUPEの旬ネタコラム
- 中古戸建て
中古住宅にホームインスペクションは必要?メリット・費用・業者選びを解説!


WRITER
鳥居 龍人
二級建築士 e-LOUPEインスペクター
中古住宅を購入するときに気になるのは、やはり建物の状態ではないでしょうか。
一見きれいに見える家でも、実は見えない場所に不具合や劣化が潜んでいることがあります。特に中古住宅は、新築と違って使用年数やメンテナンス状況がそれぞれ異なるため、内覧会や業者の説明だけでは気付けないことも少なくありません。
そこでこのコラムは、中古住宅におけるホームインスペクションの必要性や費用感、よく見つかる不具合の事例などについて詳しく解説いたします。
目次
中古住宅を買う前に「ホームインスペクション」って必要?
そもそもホームインスペクションとは?
ホームインスペクションとは、建物に関する専門知識を持ったホームインスペクターが、第三者の立場で建物の現況を確認し、わかりやすく客観的に評価するサービスです。
調査対象は基礎・外壁・屋根・床・壁などの構造部分に加え、給排水設備や屋根裏・床下など見えにくい箇所も含まれます。
調査の結果は口頭説明や報告書で共有されるため、「どこに不具合があり得るか」「どこから直すべきか」といった優先順位が理解しやすくなるのが特徴です。

中古住宅ではなぜ重要なのか
住宅を選ぶときに大切なのは、「この先も安心して住み続けられるか」「致命的な欠陥がないか」を購入前にきちんと見極めることです。ホームインスペクションを実施すれば、この2点について判断する材料が得られます。
特に中古住宅では、新築に比べて経年劣化や過去のメンテナンス履歴が不明なことが多くあります。
そのため、リフォームで内装はきれいでも、屋根や外壁の小さなひび割れから雨漏りが進行して耐久性が低下していたり、給排水設備の劣化から水漏れしているケースも少なくありません。
また、築年数が古い物件では、建築当時の基準や施工方法によって断熱材や耐震性に差がある場合もあります。
住み始めてから建物の不具合に気付いてしまうと、高額な修繕費がかかってしまったり、売主とトラブルに発展してしまうことが考えられます。そのため、中古住宅購入時において、建物の安全性や今後の費用の見通しを考える上で、事前にホームインスペクションを実施しておくことはとても重要な工程です。
やらなくて後悔する人が多い理由
実際に中古住宅購入後に予期しないトラブルに直面し、「あの時ホームインスペクションをやっていれば…」と後悔するケースは少なくありません。
たとえば、よくあるケースとしては以下の3点が挙げられます。
- 購入後すぐに雨漏りが発覚し、高額な修繕費が必要になった
- 床下でシロアリ被害が進行しており、修復が困難な状態だった
- 契約不適合責任が免責となっており、売主や仲介業者に補償を求められなかった
購入後に雨漏りやシロアリ被害などの大きな不具合が見つかると、多額の修繕費が必要だったり、場合によっては修繕が不可能なほど深刻な状態であることもあります。
こうしたトラブルに直面すると、売主に責任があるのではないかと考える方もいると思います。しかし、売主が不具合を事前に知っていた場合を除き、基本的には補償を受けられないのが実情です。
「契約不適合責任」という買主を守る制度もありますが、契約時点で免責とされているケースも多く、その場合は交渉すらできません。また免責でない場合でも、売主が行うのは最低限の修繕にとどまることが多く、仲介業者も消極的なため十分なサポートが得られない場合もあります。
そのため購入前に調査を行い、「大きな不具合がないか」「修繕にはどれくらい費用がかかるのか」など建物の現状に対するリスクについて、あらかじめ知っておくことが大切です。

事前に不具合を知っておくことで、契約内容や価格交渉の材料として使用できる場合もあります。
ホームインスペクションで分かること、チェックされる場所
ホームインスペクションは、専門家が検査をすることで、建物の状態を確認できるサービスであることを説明しました。
ここからは、より具体的な調査項目やそこからわかること、不具合の事例について解説していきます。
主な検査項目
ホームインスペクションは、建物を隅々まで検査するために、建物の外と中の両方から調査を行います。
調査する場所は大きくわけると、外周り、室内、床下、屋根裏の4箇所です。それぞれ調査項目が異なるため、1つずつ解説していきます。
| 調査する場所 | 主な検査項目 |
|---|---|
| 外周り | 屋根・外壁・基礎等のひび割れなど |
| 室内 | 床や壁の傾き、雨漏れ、建具や設備など |
| 床下 | シロアリ被害の有無、配管の劣化状態、構造部材の損傷など |
| 屋根裏 | 雨漏れ、金具の緩み、断熱材の状態など |
外周り
外周りの調査では、屋根・外壁・基礎などを確認します。
これらは雨や紫外線、自然災害の影響を強く受けるため、劣化が進んでいるケースが少なくありません。
屋根材の割れや外壁のひび割れ、基礎のクラックを確認するほか、外壁表面のチョーキングやシーリング材の劣化状況も重要なチェックポイントです。外壁や屋根など建物の一番外側に穴が開いていると、直接雨漏れにつながってしまうため、目視や高所カメラ等を使用して確認します。



外周りの調査は目視と、機材を活用した調査が行われます。調査方法は業者ごとに異なるため、希望する調査がある場合は事前に確認しましょう。
室内
室内の調査では主に床や壁の傾き、雨漏れ、建具、各種設備に関して確認します。
レーザーレベルや水平器を用いて家全体の傾きを調べたり、扉や窓がスムーズに開閉するか、雨漏れが原因と考えられるシミなどはないかチェックします。
設備関係では、換気扇がしっかり空気を吸い込んでいるかや、水周りに水漏れがないかも重要なチェックポイントです。また、床のきしみやたわみがひどい場合には、シロアリ被害が隠れている可能性もあるため、室内調査では歩きながら違和感がないかも確認しています。


床下
床下の調査では、配管の水漏れやシロアリによる被害、構造部材の劣化、基礎のひび割れなどを確認します。
構造部材の劣化は建物の耐久性に直結するため、特に重要なチェックポイントです。
通常は点検口から内部をのぞいて調べますが、その方法では一部しか確認できません。基礎や土台の割れなどを詳しく調べたい場合には、床下に実際に入り込んで調査を行う「床下進入調査」に対応した業者へ依頼することが望ましいでしょう。


屋根裏
屋根裏の調査では雨漏りの有無や金具のしめ忘れ、断熱材の不備などが主な調査項目です。
特に雨漏りは木材の劣化やカビの発生、シロアリの誘引につながり、放置すると建物全体の耐久性を下げる原因になります。
調査方法としては床下と同様、点検口から覗き込む簡易的な確認が一般的です。しかし、実際には点検口の近くでは異常が見つからず、奥に進入して初めて雨染みや断熱材の欠損が判明するケースもあります。
そのため、屋根裏の状態を正確に把握するためには、調査員が内部に入り込んで確認する「進入調査」が欠かせません。



e-LOUPEでは床下・屋根裏ともに可能であれば進入調査を行い、隅々まで確認しています。
検査で見つかることの多い不具合事例
中古住宅では、経年劣化による不具合がよく見つかりますが、購入後に発覚すると高額な修繕費がかかったり、日常生活に支障をきたす可能性もあります。
ここでは中古住宅でよく見つかる不具合について、実際の調査で見つけた事例をもとに解説していきます。
浴室周りの断熱材未設置
浴室周りの断熱材が設置されていないという状態は、築20年ほどの物件でよく確認されます。
現在では浴室の寒暖差が危険というヒートショックに関して認識が広がってきましたが、当時はそこまで重要視されておらず、断熱材が全然入っていない物件も少なくありませんでした。

ユニットバス自体の交換を行う際には、断熱材の増設を検討したいですね。
外壁のシーリング剥離、ひび割れ

劣化が始まった外壁では、窓まわりや配管まわりのシーリングに細かなヒビが入ることがあります。
塗装工事などのメンテナンスを行わずに放置していると劣化し、最終的にはシーリングが大きく剥がれ落ち、そこから雨水が浸入してしまいます。
こうした状態になると壁内部の構造材を早く劣化させてしまうため、できるだけ早めの修繕が望ましい不具合です。
屋根材の劣化

屋根材は普段は目視で確認することが難しい部分ですが、風雨や紫外線、自然災害の影響を強く受けるため劣化しやすい箇所です。
特に台風や強風の後には劣化やずれが進行しやすく、雨漏りの直接的な原因となります。さらに、屋根材が剥がれたりずれたりすると落下の危険が生じ、自宅だけでなく近隣の建物や通行人に被害を及ぼす可能性もあります。
見えない不具合「シロアリ・雨漏り・傾き」はチェックできる?
住宅について調査するなら、一番気になるのは普段見ることのない場所での不具合ではないでしょうか?
ここでは、住宅の安全や安心に直結する部分であるシロアリ被害、雨漏り、建物の傾きについてどこまで調査できるのか解説していきます。
シロアリに関して
シロアリ被害の有無は、室内調査と床下調査で判断します。
多くのシロアリは湿気が溜まりやすい場所を好み、湿った木材を餌にします。そのため、湿気の溜まりやすい床下や玄関、浴室や水周りなどでシロアリ被害の痕跡を見つけることができます。
室内など比較的に確認しやすいシロアリ被害もありますが、実際にはシロアリ被害であるかを確認するためには床下側で調査をしないと原因がわからないことも多くあります。
シロアリ被害の心配がないかしっかりと確認したい場合には、床下進入を伴う調査がおすすめです。
シロアリ被害が進むと、建物を支える構造部材に被害を広げ、耐久性が大幅に下がってしまいます。防蟻処理、補修、部材交換を行う費用は、数十万〜数百万円に及ぶことがあるため、シロアリ被害の有無についてはチェックしておきたいポイントですね。


雨漏りに関して
雨漏りに関しては、屋根裏や床下に入って濡れ跡や湿った木部を確認できると、どこから漏れているかを詳しく確認することが可能です。濡れている箇所に近づける場合は含水率計で数値化し、過去の雨漏れか現在も進行中かを判断することができます。
室内の壁や天井に雨染みは、比較的容易に確認できるポイントですが、目視での判断が難しい壁の中に関しては会社ごとに対応が分かれます。サーモグラフィを使用した非破壊による壁内調査を行う業者もあるため、壁内の雨漏りについて気になる場合は、調査方法について確認することをおすすめします。
雨漏りは木材を劣化させるだけでなく、シロアリを誘引する原因にもなるため、購入前に必ず確認しておきましょう。


建物の傾きに関して
物件の傾きは、床と壁の双方を計測します。
レーザーレベルやデジタル傾斜計を用い、各室の複数ポイントの高さ・傾斜を測って傾きの度合いを確認しています。
付近に擁壁がある、川や水路が近い、排水計画や地下水位の影響が考えられる場合など、周辺環境も踏まえて今後どのような傾向が生じる可能性があるかを判断することも可能です。


ホームインスペクションはどのタイミングで行えばいい?

中古住宅の購入は、一般的に内見→申し込み→契約→引き渡しの順で進みます。
ホームインスペクションのタイミングとしては、物件購入の契約前に行うことが望ましいです。
これは契約後のインスペクションで著しい不具合が見つかり、申し込みを解消しようとした場合、支払った分の申し込み金が帰ってこないためです。
可能な限り契約前に物件を確認し、ご自身にとって不利な状況にならないようにすることを推奨しています。
ベストは契約前だが、実施は難しい
インスペクションの実施は契約前が望ましいのですが、さまざまな理由で売主に断られてしまうことが少なくありません。
代表的な理由として以下の3つの理由があげられます。
- 売主や不動産会社が調査を拒否する
- 特に売主がまだ居住中の住宅では、断られることが多くあります。
たとえば、購入が未定の段階で調査に長時間使いたくない、またプライバシーの観点から家の写真を撮られたくないという理由で断られることがあります。不動産会社や仲介業者側も、日程調整や立ち会いで手間が増えるため、調査を希望しないお客さまの対応を優先するケースも少なくありません。
- 不動産売買の日程的タイミングが合わない
- 不動産売買は、申し込みから契約まで約2週間ほどで取引が進んでいきます。
調査を行う際は、売主・買主・仲介・ホームインスペクション業者等のスケジュールを合わせる必要があります。立会い人数が増えるほど日程が合いにくくなり、この2週間の間で調査を実施することが難しくなりがちです。

ホームインスペクションの存在を直前で知ったため、予定が合わないという理由で泣く泣く諦めた方もいらっしゃいました。
- 売主がすでに第三者調査を実施済みだった場合
- 稀に売主が第三者機関に依頼し、調査を行っているため「新たな調査は必要ない」と断られる場合があります。ラッキーと思う方もいるかもしれませんが、調査として不十分なケースがあるため、注意が必要です。
以前不動産会社が売主で、第三者機関と言いつつ自社社員に物件を見回らせ書類を作成していた事例があります。
調査内容として、屋根裏や床下の進入調査をしない、水道の通水を確認しないなどの簡易検査にとどまり、簡易的な写真だけがまとめられた書類が作成されていました。
内容は不十分でも調査結果が記された書類としては残っているため、素人の方がその書類から住宅の状態を判断するのは難しいかもしれません。
誰が、どの範囲を調べたのかを確認し、必要であれば中立な立場のインスペクション業者に再調査を依頼するのがおすすめです。
多くは契約後〜引き渡し前のタイミングで実施
中古住宅においてホームインスペクションのベストな時期は契約前ですが、前項の理由からお断りされることも少なくありません。
そのため、契約後〜引き渡し前で実施されるケースが大半です。このタイミングでは契約が成立しているため、売主の同意を得やすいという利点があります。
一方で、重大な不具合が見つかっても契約を白紙に戻すのは難しいのが実情です。ただし、調査結果を根拠に価格見直しや引き渡しまでの是正工事など、契約条件の交渉はできます。
入居してから不具合に気付くより、調査結果にもとづいて修繕すべき箇所やメンテナンスの優先順位・費用感を把握できることが大切ですね。

ホームインスペクションの所要時間と費用はどのくらい?
所要時間の相場
一般的な木造2階建て住宅の調査がスムーズに進めば、調査時間はだいたい2〜3時間程度が目安です。
ただし建物の面積が広い場合や、雨漏りに起因する不具合や構造に関する不具合等に関して著しい状況が確認された場合は、調査時間も比例して長くなる可能性があります。
売主居住中の調査の場合、調査時間が伸びてしまうとトラブルになる可能性があるため、事前に時間が延びる可能性に関して伝えておきましょう。
また、オプション調査が多ければ調査時間も長くなります。屋根裏や床下への進入調査を含んでいる場合は、3〜4時間程度の調査時間が必要です。
ポイント
・一般的な木造2階建てであれば、所要時間は約2〜3時間
・オプション調査をつけると、約3〜4時間かかる
・建物面積や不具合の多さによって、調査時間は伸びる
ホームインスペクションの金額相場
国土交通省の「インスペクションガイドライン」に則った中古住宅の調査であれば7~9万円程が相場になります。
このガイドラインは最低限の調査内容となっている為、多くのホームインスペクションを行っている調査会社は、基本的な調査の他に設備点検や屋根裏、床下への進入調査などを「有料オプション制」にしているところがほとんどです。最近では、報告書作成もオプションとする業者が増えてきました。
これらオプションを加えると、調査費用の総額はだいたい13万~17万円程になることがあります。
依頼先を選ぶ際はか価格だけでなく、調査範囲や報告書の質、調査後のアフターフォローまで確認しましょう。

参考までにe-LOUPEでは、床下・小屋裏進入や設備点検、写真付き報告書までを標準メニューに含めたプランで、12万円(税込132,000円)にてご案内しております。
どこに依頼する?不動産会社の紹介と第三者業者の違い
中古住宅の調査をしようと思ったときに、まず悩むのが「どこに相談すればいいのか」ではないでしょうか。
一番身近な不動産会社から紹介された業者にお願いするのが無難なのか、それとも自分で第三者業者を探した方がいいのかと迷う方も多いはずです。
依頼先の選び方について、不動産会社の紹介と第三者業者、それぞれの特徴を整理すると以下のポイントに分けられます。
| 不動産業者 | 第三者業者 | |
|---|---|---|
| メリット | ・業者を探す手間が省ける ・施工店との連携などがスムーズで日程調整がしやすい |
・調査結果に忖度がない ・購入時に必要なリアルな情報が得られる |
| デメリット | ・不動産業者と日常的に取引のある業者の可能性がある ・中立な視点での調査が可能か不明 |
・業者探しが大変 ・調査内容に関して各社にかなりばらつきがある |
不動産業者

- メリット
- ・業者を探す手間が省ける
・施工店との連携などがスムーズで日程調整がしやすい不動産業者がインスペクション業者を手配してくれるため、業者選びで迷ったり買主主導でスケジュールを調整する必要がない点が大きなメリットです。忙しい方にとってはありがたい点ですね。
- デメリット
- ・不動産業者と日常的に取引のある、パートナー業者の可能性がある
・中立な視点での調査が可能かどうか不明である売主・仲介側とつながりがある場合、「物件を売る前提」での調査になりやすく、指摘が控えめになる場合があります。
もちろんすべての業者がそうというわけではありませんが、調査の透明性を重視するなら、この点は十分考慮しておきたいところです。
第三者業者

- メリット
- ・調査結果に忖度がない
・購入時に必要なリアルな情報が得られる業者を売主が選ぶことで、インスペクターの視点が売主や仲介業者に偏らない点が大きなメリットです。「この物件本当に買って大丈夫なのかな…」という不安に対して、客観的な視点で判断することができます。
- デメリット
- ・業者探しが大変
・調査内容に関して各社にかなりばらつきがあるインスペクション業者は数多くあり、それぞれの専門性によって得意なことが分かれています。
基本的なインスペクションガイドライン上の調査の他にも、よし詳しい調査を行える業者もいるため、自身が依頼したい調査を実施できる業者を探すのに時間がかかる可能性があります。
よくある疑問に答えます(Q&A形式)
Q.検査で欠陥が見つかったら購入は中止になるの?
契約前であれば、購入を見送ることも選択肢に入ります。
しかし、多くの場合は契約後に調査を行っている方がほとんどのため、購入を中止される方は少ない印象があります。
その理由としては、契約後に購入を中止すると、原則として契約金は戻ってこないという点が挙げられます。
契約金が戻ってこなくてもいいと思えるほど大きな不具合や欠陥があれば、購入を中止することも検討すべきですが、多くはそこまで酷い不具合ではありません。
そこまでひどい不具合でなければ、その結果をもとに売主に対して価格交渉をおこなったり、不具合の修繕に関して打診してみる方がメリットが多いことがあるため、まずは交渉してみるのがおすすめです。
Q.調査結果を売主や仲介に絶対に共有しなくてはいけない?
これは非常に難しい問題ですが、原則として報告先は依頼者(買主)です。そのうえで同席されている方に結果を共有するかについては依頼者の匙加減となります。
中古住宅でインスペクションを実施される方の中には、売主に調査結果を知られることを好まない方も一定数いらっしゃいます。
調査結果の共有を共有したくない方は、事前に業者と打ち合わせをしておきましょう。
Q.調査時の立会いは必須?
調査時の立会は必須ではありません。
様々な理由から調査当日にお立会いをしない方がいらっしゃるため、調査後の電話やメールで調査結果のみをご報告する場合もあります。
ですが調査に立ち会うことで、指摘事項のご報告や修繕に関しての目安以外の情報も得られる可能性があります。
特に家主が居住中の場合、物件の修繕履歴(リフォーム歴)や近隣の状況を売主から直接聞くことも可能です。
近隣の状況は引っ越す前に知っておくと、購入前から気を付けることがはっきりとしたり、購入に関する判断材料にすることができるため、可能であれば調査に立ち会うことをおすすめします。
Q.売主は補修義務ってあるの?
契約書の契約不適合責任が免責になっていれば、売主に補修を請求することは難しいです。
中古住宅の売主の多くはできれば何もせずそのまま売りたいと考えています。
「契約不適合責任が免責」となっている場合、引き渡し前であれば、購入金額の値引きや修繕に関して交渉できますが、引き渡しが済んでいる場合はそもそも交渉することすらできません。
契約不適合責任があれば、引き渡し後でも売主が最低限の処置の対応はしてくれます。しかし最低限となるため満足度が低い結果となりやすく、仲介業者も積極的に動いてくれないことが多いです。
基本的に義務ではないので中古住宅を購入するときは、メンテナンス費用も必要になるということを、あらかじめ念頭に置いた上で物件探しをしましょう。
Q.調査を依頼することで売主や仲介業者とトラブルにならない?
事前連絡と合意があれば通常は問題ありません。
売主や仲介業者とトラブルとなるのは、何も告げずに内覧当日にホームインスペクション業者を呼ぶケースです。
事前にホームインスペクションを実施したいという意思を伝えていなければ、抜き打ち検査のように感じられてしまい、良い印象は持たないでしょう。また、当日になって急に「調査に3時間かかります」と言われて、対応してくれる売主もほとんどいません。
また、トラブルとなりやすいケースとしては、売主がホームインスペクションに対して前向きでないケースです。
売却予定の物件に関して、売主が調査を断ることはほとんどありませんが、拘束時間が長いことやめんどくさい等、断られてしまう場合もあります。
売主、仲介業者とのトラブルを避けるためには、調査を行いたい側と売主・仲介双方の意見のすり合わせが大切なポイントになってきます。くれぐれも売主・仲介に相談なくホームインスペクションの実施をすることはやめましょう。
まとめ
今回は中古住宅購入時のホームインスペクションに関して、そもそも必要かどうかに関して解説していきました。
中古住宅購入時にホームインスペクションを行うことで
- 見えないリスクが可視化できる
- 購入後に必要な修繕等の費用に見通しが立つ
- 調査結果をもとに契約内容に関して交渉することができる
というメリットがあります。
住宅の購入は人生の中でも大きな買い物です。
ホームインスペクションを利用することで、今後も安心して住み続けられるのか、設備等に不備はないかなど事前に把握し、後悔のない住宅選びをしていただければと思います。
屋根から床下まで診る!明快料金のインスペクション

シンプルプランで選ぶ必要なし!
Google口コミ4.9業界最高水準
床下・屋根・屋根裏の点検も実施!
創業50年、住宅を知り尽くすプロ
重厚な報告書が将来の宝に
自社社員の建築士が第三者の立場で皆様の新築・中古・自宅を調査。150を超える項目と専用の診断機器を使って家の隅々までチェックします。1974年創業、50年の歴史と7万件を超える戸建て物件の床下・屋根裏調査実績から、おかげさまでGoogle口コミ200件超4.9の高評価をいただいております。