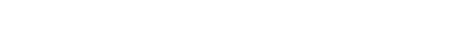e-LOUPEの旬ネタコラム
- 中古戸建て
- 自宅向け
ホームインスペクションの調査結果で言えること、言えないこと


WRITER
鳥居 龍人
二級建築士 e-LOUPEインスペクター
こんにちは。e-LOUPEの鳥居です。
「中古戸建ての購入を検討しています。不動産業者の人は『しっかりした建物だから問題ない』と言ってますが実際あとどれくらい住めるのか、ホームインスペクションで見てもらえますか?」
以前このようにお問合せいただいたことがありました。
結論から言うと、残念ながらホームインスペクションの調査結果ではこちらの問いにはお答えできません。
今回はホームインスペクションで明言できること、できないことについてお話ししていきます。
目次
ホームインスペクターが明言できないこと

ホームインスペクションにおいて
「あと何年住めるか」
「どれくらいの地震に耐えられるか」
などの明言は困難です。
ホームインスペクションはあくまでも「建物のどこがどんな状態か」という現在の劣化や不具合を調べるためのものであり、「この家だったらあと何年は持つ」という視点での調査はとても難しいのです。
「いや、実際はこれくらいですよ。」といったお答えをすることはできませんので、事前に認識はしておいた方がいいでしょう。
ホームインスペクションの調査結果をどう活かす?

では今回のような状況では、ホームインスペクションはお勧めできないのかというと、そうとも言い切れません。
どんなメリットがあるのでしょうか。
隠れた不具合からの状況推定
まず考えられるのは「隠れた不具合の発見」です。
ホームインスペクションでは床下や小屋裏も調査しますので、雨漏れや白蟻被害などの状況をチェックすることができます。
もし大きな不具合が見つかるようであれば、それだけ建物の寿命にも弊害を及ぼしていることになりますので、それらの情報を元に中古物件を買うか買わないかの判断をする事ができます。
リフォーム前提での購入判断
また、もう1つの活用法として「リフォームの参考にする」というものがあります。
中古住宅はリフォームを前提にして購入を検討される方がとても多いです。
しかしどの部位でどの程度の劣化や不具合が発生しているのかをちゃんと把握しておかないと、後になって新たな不具合が発覚したり本来直すべき箇所の修繕を怠ってしまうことになりかねません。
確かにリフォームをすれば例え部材が傷んでいたとしてもたいていのことは改善できますし、場合によっては建築当初よりもより強固にすることも可能です。
ただし、予算も限られている中でどこまで建物の修繕に費用をかけるのか?まずは全体の状況を把握することが大切となります。
この先何年住めるかは建物のメンテナンス次第で常に変わります。
ホームインスペクションは住まいを長持ちさせるための「リフォームの優先順位の計画」を立てる上でも非常に役立つのです。
建物の安全性を裏付けるために必要なこと

ただし、今回のケースで注意すべきは建物の「耐震性」です。
家屋の耐震性能の決まりは「建築基準法」に明記されていますが、その条文は過去に何度も「これでは不十分」と変更が加えられてきました。
もし築年数がかなり古い住宅なようであれば、現行の耐震基準を満たしていない可能性が考えられます。
目安として1981年6月の新耐震基準より以前の建築であれば注意が必要です。
もし売主が「しっかりした建物だから大丈夫」と言っていた場合、「しっかり」について
- どんな耐震改修工事を実施したのか
- 耐震診断の結果安全だったのか
などをもっと詳しく確認する必要があります。
とにかく大事なのは具体的な裏付けですので、何となくのイメージで判断するのではなく、しっかりと確認を行いましょう。
”事実”を報告するホームインスペクションの調査結果
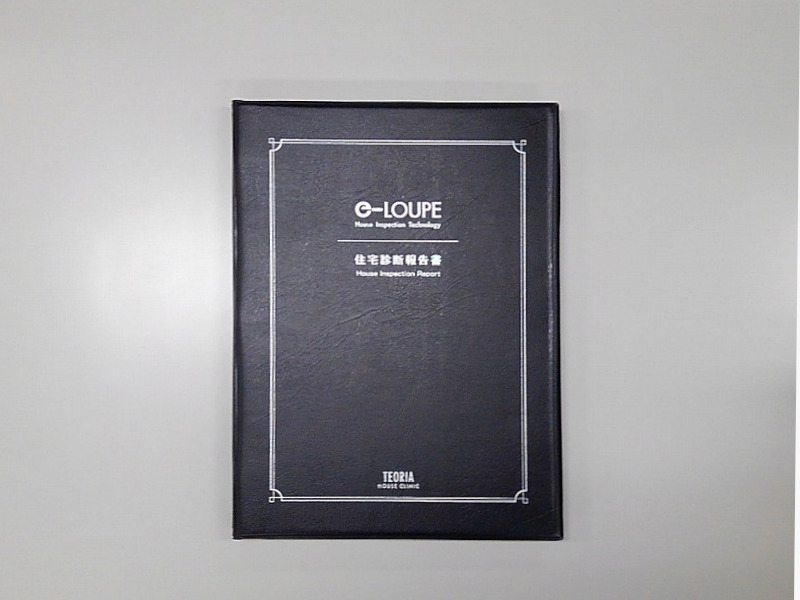
不動産業者は物件を売ることで利益を得ていることから、「とりあえず売ってしまえばこっちのもんだ」と考える心無い業者も中には存在します。
「この物件はまだ痛みもそんなにないですし、元の持ち主さんもきれいに使っていたのでいい物件ですね」
「引き渡し前に部分的なリフォームをするので殆ど新品と変わりませんよ」
「築浅ですし、お買い得ですね」
これらの言葉はいわゆる「売り文句」に過ぎません。
その証拠に、実際に小屋裏や床下の状況を確認したり、屋根がどうなっているか、外壁に不備はないかまで調べた上で発言されている業者さんに私は出会ったことがありません。
言われたことを鵜呑みにするのではなく、「もしかしたら何かあるかも?」と少し考えてみて、気になることを不動産業者へ訪ねてみましょう。
もし不動産業者から曖昧な回答しか得られずに不安なようでしたら、事実を明確にするホームインスペクションを活用いただくのがいいのではないかと思います。
さいごに
今回は、ホームインスペクションの診断結果で明確にわかるものとそうでないものの違いについてお話ししてきました。
ホームインスペクションを活用するには、「何をしてくれるのか」以上に「まず前提として購入物件に何を求めているか」も重要となることを覚えておきましょう。
ホームインスペクションをご活用の際は、こちらのページも併せて参考にしていただけると嬉しいです。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
「見えないところへの徹底した追求」がe-LOUPEの基本方針です。