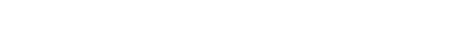e-LOUPEの旬ネタコラム
- 新築戸建て
- 中古戸建て
- 自宅向け
木造住宅の耐用年数とは?寿命を延ばす秘訣について解説!


WRITER
岩井 数行
二級建築士 e-LOUPEインスペクター
「木造住宅の寿命は30年って本当?」
「耐用年数は22年って見たけど、寿命とは違うの?」
木造住宅の寿命で検索すると、30年や22年といった数字を目にすることがあります。木造住宅を購入予定の方や売却を考えている方にとって、寿命が短いという情報は気になるポイントではないでしょうか。
しかし、木造住宅の平均寿命は約65年といわれており、実際に築100年を超える古民家も存在します。適切なメンテナンスさえ行えば、木造住宅は想像以上に長く住み続けることも可能なのです。
このコラムでは、「木造住宅は寿命が短い」と言われている理由や寿命と耐用年数との違い、そして木造住宅を長く快適に保つためのメンテナンスについてわかりやすくご紹介します。
目次
木造住宅の寿命は30年?
「木造住宅は30年程度で寿命を迎える」と言われている背景には、1996年に国土交通省が発表した建設白書があります。この建設白書には、日本の住宅の平均寿命は約26年とされており、諸外国と比較すると短いことが記載されています。

この平均寿命が短いとされる理由には、大きく2つの要因があります。
1つ目はこの平均寿命というのが、「過去5年間に取り壊された住宅の築年数の平均値」であるということです。
つまり、取り壊された住宅の中には、建て替えや間取りを変えるために解体されたものやリフォーム費用の高さから解体されたものまで、さまざまな理由で取り壊された住宅も多く含まれているということです。
2つ目の要因には、戦後の急速な住宅需要に対応する中で、質より量を優先して建てられた住宅が多かったという時代背景があります。そのため、質の低い住宅の大量建設・大量廃棄の構造を作り出してしまい、実際に寿命の短い住宅が多かったのです。
しかし現在では建築技術が進歩し、住宅の標準的な性能も大きく向上しています。2011年の調査では、木造住宅の平均寿命は1997年の約44年から約65年へと延びているという結果も発表されています。(出典:国土交通省「【指針参考資料5】建物の平均寿命について」)

このように背景を整理すると、「木造住宅は30年で寿命」という見方は、あくまで過去の住宅事情に基づくものであり、現在の木造住宅に必ずしも当てはまらないんですね。
木造住宅の耐用年数とは?
耐用年数について調べると「22年」という数字がよく出てきますが、これは税務上で定められた「法定耐用年数」のことです。
実際には、耐用年数には複数の種類があり、それぞれが異なる目的や意味を持っています。
以下に、主な4種類の耐用年数について整理します。
| 法定耐用年数 | 税務上の減価償却を目的として、国税庁が定めている年数。木造住宅では「22年」とされており、この期間を超えると帳簿上の価値はゼロと見なされる。(出典:国税庁「主な減価償却試算の耐用年数表」) |
|---|---|
| 経済的耐用年数 | 経済的耐用年数とは、市場で試算としての価値があると評価される年数。これは、建物の立地条件、間取り、設備のトレンド、周辺環境の変化などによって変動する。 |
| 物理的耐用年数 | 建物の構造そのものが物理的・科学的な要因により劣化して、住宅としての性能を果たせなくなるまでの年数。使用する材料の質や施工の丁寧さ、気候条件、定期的なメンテナンスの有無によって大きく変動する。 |
| 期待耐用年数 | 適切な維持管理が行われることを前提に、住宅が安全かつ快適に使い続けられると見込まれる年数。中古住宅市場などで、購入希望者が物件の将来性を判断する目安として活用される。住宅性能表示制度などで用いられ、構造だけでなく、設備や内装なども含めた全体的な居住性が基準となる。 |
気をつけていただきたいのは、法定耐用年数はあくまで減価償却などの税務計算をするために定められた年数であるということです。法定耐用年数を超えたからといって住宅が使えなくなるわけではありません。
耐用年数=寿命ではない
ここで特に強調したいのは、「耐用年数=寿命ではない」ということです。
耐用年数とは、住宅の状態や価値を判断するための基準や目安であり、必ずしもその年数を超えたら住めなくなるわけではありません。
たとえば、法定耐用年数は税務計算上の目安であり、物理的耐用年数は建物の構造や材料に基づく工学的な推定値です。これらはいずれも“参考値”であって、”住めるかどうか”の判断基準ではないのです。
一方、住宅の寿命は、日頃の使い方や維持管理によって大きく左右されます。定期的な点検や補修を行えば、耐用年数を超えても安全で快適に住み続けられる住宅は数多くあります。

木造住宅を長持ちさせるためには
木造住宅は、適切なメンテナンスを行うことで寿命を延ばすことができます。逆を言えば構造や設備が良好であっても、定期的な手入れを怠れば、思ったより早く劣化が進んでしまう可能性もあるということです。
定期的なメンテナンスが必要な箇所は大きく分けると7つあります。
- 構造体
- 屋根
- 外壁
- バルコニー
- 外部建具
- 室内
- 住宅設備
ここでは日常的なメンテナンスが必要な箇所と定期的なメンテナンスが必要な箇所の2つについて解説します。
日常的なメンテナンスが必要な箇所
日常的にできるメンテナンスとしてこまめな掃除や日常生活から感じる異変がないかチェックするということがあげられます。
| 外部建具 | 玄関ドアや窓サッシ、シャッターなど | 作動時の異常や異音を感じたら、早めに補修し、消耗品は交換をする。月に一度は窓のレールのほこりやゴミの掃除を行う。 |
|---|---|---|
| 室内 | 内装材やフローリングなど | 日常的なフローリングの乾拭き。ドアや窓の可動部のシリコンスプレー塗布や建具を調整する。 |
| 住宅設備 | 給排水設備など | 使用しているうちにたまる汚れは異臭やつまりの原因となるため、定期的に洗浄を行う。 |
定期的なメンテナンスが必要な箇所
日常的なお手入れに加えて、定期的に住宅の修繕やリフォームを実施しましょう。
| 構造体 | 防蟻処理 | 5~10年ごとにシロアリ防除処理を繰り返し行う。 |
|---|---|---|
| 屋根 | ストレート屋根や鋼板屋根 | 10~20年ごとに表面の塗装、20~40年ごとに増張りや葺替えを行う。 |
| 外壁 | サイディング・ALC | 10~20年ごとに目地の打ち替えや塗装を行い、20~40年で貼替えを行う。 |
| バルコニー | 防水層、FRPなど | 10~20年ごとに重ね塗りを行う。 |
| 室内 | 5~10年ごとに部分補修や貼替えを行う。 |
実際の劣化状況は住宅が置かれている環境や使用状況によって大きく異なります。たとえば、日当たりの良い場所ではかなり劣化スピードがかなり早くなりますが、全く日が当たらない場所ではゆっくりと劣化してくため、同じ素材を使用していても差が出てくるのです。
また、地震や台風によって補修が必要になる場合もあるため、日頃から上記の部位に関して劣化している箇所はないか確認する習慣をつけておくと良いでしょう。
ホームインスペクションの活用を
しかし、屋根の上や床下など、普段の生活では確認しづらい場所も多くあります。そんなときはホームインスペクションを利用すると良いでしょう。プロによる点検を受けることで、見えない部分も含めて建物全体の状態を把握し、適切なメンテナンス時期や費用について判断することができます。

ホームインスペクションとは、住宅の劣化や不具合、補修の必要性について、建築の専門知識を持つ第三者が中立的な立場で調査するサービスで、新築・既存住宅を問わず利用されることが増えています。
たとえば新築では施工状況の確認に役立ち、中古住宅では劣化状況の把握を通じて購入判断の参考となります。また、自宅についても10年や15年ごとに点検を行うことで、メンテナンスの時期を適切に見極めることが可能です。
▼ホームインスペクションについて知りたい方はこちら
ホームインスペクションとは?メリット・費用・流れを解説|e-LOUPE
まとめ
「木造住宅は30年しかもたない」というイメージは、過去の情報に基づいた誤解であることが多く、実際の寿命は適切なメンテナンスによって延ばすことができます。そのため、耐用年数の定義を正しく理解し、建物の本質的な寿命を見極めることが重要です。
適切な維持管理を行えば、木造住宅は60年、70年、あるいはそれ以上にわたって快適に住み続けられます。購入や売却、建て替えを考える際には、耐用年数だけでなく建物の状態そのものをしっかりと確認して判断することが大切です。
そのためにも、ホームインスペクションをうまく活用して、安心・納得のいく住まい選びをしていただければと思います。
屋根から床下まで診る!明快料金のインスペクション

シンプルプランで選ぶ必要なし!
Google口コミ4.9業界最高水準
床下・屋根・屋根裏の点検も実施!
創業50年、住宅を知り尽くすプロ
重厚な報告書が将来の宝に
自社社員の建築士が第三者の立場で皆様の新築・中古・自宅を調査。150を超える項目と専用の診断機器を使って家の隅々までチェックします。1974年創業、50年の歴史と7万件を超える戸建て物件の床下・屋根裏調査実績から、おかげさまでGoogle口コミ200件超4.9の高評価をいただいております。